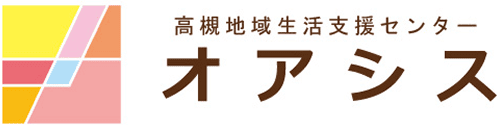福祉部長のひとり言

福祉部長のひとり言 44 『地域共生社会のイメージ 』
幼いころ、大人たちから幾度となくかけられてきた言葉の一つに「人に迷惑をかけたらあかん」がある。「人に迷惑をかけたことのない人」はいないのに。
人と人との間にはいくつもの迷惑が存在し、迷惑と感じることも人によって違う。乳幼児は大人の力を借りないと生きていけない。高齢になれば身体は老い、認知症になっていく。ピンピンコロリと逝ったとて、自分の力で火葬場に行き、墓に入れる人などいないのだ。
「人に迷惑をかけたらあかん」の「人」とは「他人様」である。こうして育児や介護の問題が「家族で何とかしないと…」につながっていく。介護殺人や虐待はこうした家族の「負担」から生み出される。
水俣で水俣病患者相談をされている水野三智さんの著書(注1)には「安心して迷惑をかけあえる地域社会づくり」を目指していると書かれていた。社会福祉法人浦川ベテルの家では「安心してサボれる職場づくり」を目指している。迷惑は、地域社会にとって、職場にとって前提なのだ。
「迷惑をかけあえる地域社会」や「サボれる職場」こそ、障害の社会モデルであり、合理的配慮なのではないか。
厚労省のポータルサイトでは、地域共生社会について「住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」としているが、それは一体どんな社会なのか…。今の制度では、障害認定や介護認定を受けることで、学校や地域とのつながりが絶たれ、希薄になっていってしまいかねない。まず、地域の学校がインクルーシブ教育(注3)を行っていない中で、地域共生社会など目指せるものだろうかとも思う。
「安心して迷惑をかけあえる地域社会」は中々見えないが、「安心して迷惑をかけあえる場や関係」を地域のあちらこちらで作り出していくことなのかな、と考えている。
(注1)みな、やっとの思いで坂をのぼる 水俣病患者相談のいま 永野三智著
(注2)社会福祉法人浦川ベテルの家